漢方薬は「食前」または「食間」に飲んでくださいって言われることが多いと思います。
なぜそのタイミングなのか、化学的視点から解説します!
「食前」、「食間」とは?
医薬品には、その薬が安全に効果が出せるよう、飲むタイミングが決められているものがあります。その一例として、漢方薬は「食前」と「食間」を指定されることが多いです。
「食前」 食事の約30分前
「食間」 食事の2~3時間後
「食間」を食事中と思われる方が多いですが、食事と食事との間という意味ですので注意です。
このタイミングから、「食前」と「食間」は空腹時であることがわかります。
なぜ、漢方薬は空腹時で服用するようになっているのでしょうか?
理由①腸からの吸収を良くするため
漢方に含まれる有効成分の中には「配糖体」というものがあります。これは、有機化合物(有効成分の本体)に糖成分がくっついているものです。
(例)甘草(グリチルリチン酸)、芍薬(ペオニフロリン)、葛根(プエラリン)、大黄(センノシド)、柴胡(サイコサポニン)など
有機化合物は脂っぽい性質(脂溶性)、糖成分は水っぽい性質(水溶性)を持っています。
腸管は基本的に脂溶性が高いものほど吸収されやすくなっています。
配糖体のままだと脂溶性と水溶性が両方あり吸収されにくいですが、腸内細菌によって分解されることで有効成分と糖成分が別々となり、脂溶性が高い有効成分が吸収されやすくなります。
空腹時に服用することで食物の影響を受けずに腸まで速く届き腸内細菌に代謝されるので、効果をより出すことができます。
理由②副作用を予防するため
漢方に含まれる有効成分のうち、「アルカロイド」というものがあります。
(例) 麻黄(エフェドリン)、附子(アコニチン)
アルカロイドは、塩基(アルカリ)性です。
平常時胃内のpHは約1.5~3.5です。胃内に食物が入ってくると、胃液が薄まりpHが上がります。最大6までいく可能性がありますが、胃酸が分泌されるため消化中に再び低下していきます。
pH=1.5~3.5の時と比べてpHが大きい食後の状態だと、吸収されやすい分子型の割合が増え、吸収率が上がってしまいます。
吸収率が上がると、動悸(胸がドキドキする)、不眠などの副作用が出現する確率も上がってしまいます。このような副作用を抑えるためにも、pHが低い状態である空腹時に飲む必要があるのです。
胃酸の分泌を抑える薬を飲んでいる場合でも、アルカロイドが吸収されやすくなってしまうので注意です。
飲み忘れた場合は?
とはいえ、「食前」や「食間」に飲むのはなかなか難しいですよね。
基本、気付いた場合に服用でも差し支えありません。その場合は以下の事に気を付けてください。
・服用後、1~2時間は食事をとらない
・次の服用タイミングを、1日3回の場合は6時間、1日2回の場合は12時間程度空ける
飲み忘れが多い場合などは、食後でも飲んだ方が効果的であるという考えもあります。
医師によっても考え方が異なるので、薬を処方してもらった医師の指示通りに服用することをおすすめします。
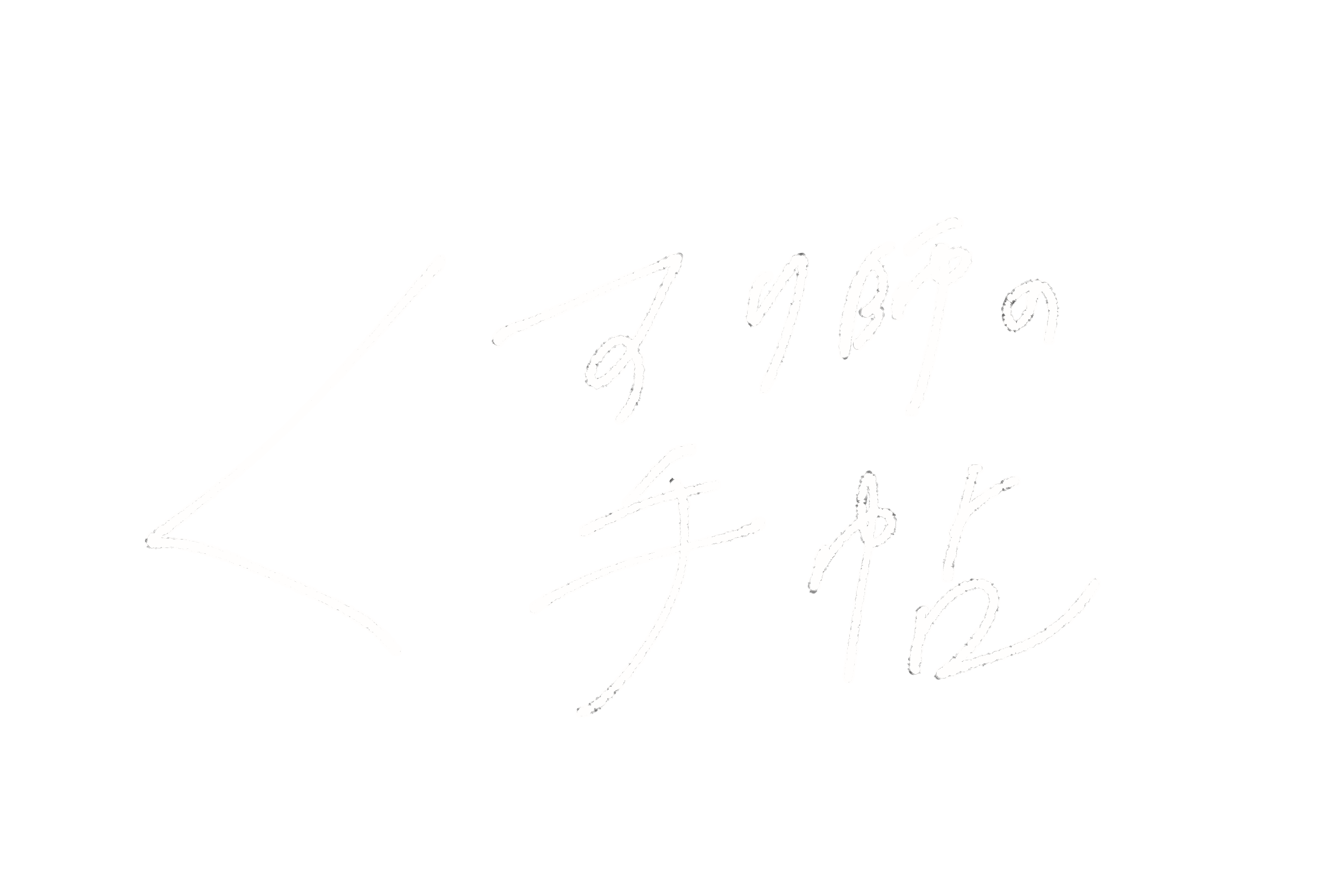











コメント