風邪を引いた時や痛みがある時など、誰しも解熱鎮痛剤を使ったことがあるのではないでしょうか?
その時に、一緒に胃薬も処方されたこともあるかもしれません。
実は、解熱鎮痛剤の中には胃を悪くする副作用があります。
今回は、副作用が起こる仕組みからその予防まで解説していきます。
解熱鎮痛剤の種類
解熱鎮痛剤は大きくわけて2種類あります。
アセトアミノフェン
市販薬:タイレノール®、バファリンルナJ等
非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs:Non-Steroidal Anti-inflammatory Drugs)
ロキソプロフェン
市販薬:ロキソニンS等
イブプロフェン
市販薬:リングルアイビー、イブ等
など
両者の違いは、下記の記事で解説しています。
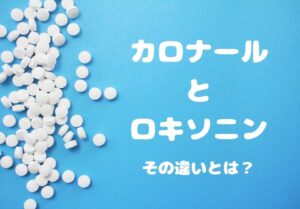
なぜ胃が悪くなる?
胃が悪くなるのは、解熱鎮痛剤のうちNSAIDsで起こることが多いです。
NSAIDsはシクロオキシゲナーゼ(COX)という酵素を阻害することで、発熱や痛み、炎症を和らげます。
このCOXには、2つの種類があります。
COX-1:全身の組織に存在している。身体の機能を保つ作用がある。
COX-2:炎症が起きた時に現れる。炎症や痛みを起こす作用がある。
多くのNSAIDsは、COX-1とCOX-2を両方阻害するため、炎症を起こす物質とともに、胃酸を減らしたり粘液を増やす物質も減らしてしまいます。
胃酸から粘膜を守ってくれる粘液が減る上、胃酸の量が増えてしまうため、胃や十二指腸、小腸の粘膜が刺激を受けやすい状態になってしまいます。
加えて、NSAIDsのうち酸性のもの(ロキソプロフェン、イブプロフェンなど)は、胃内部が酸性であることによりイオン型となり、胃の細胞内に取り込まれて細胞を障害します。
このようにして刺激を受けた消化管粘膜には、以下のような症状があらわれてしまいます。
胃腸管刺激症状
(胃のもたれ、食欲低下、胸やけ、胃が痛い、嘔吐、黒い便など)
消化性潰瘍
消化管の壁が深く傷ついた状態
また、以下の方は副作用が起こりやすい可能性があるので注意しましょう。
・高齢者
・消化性潰瘍(特に出血性)になったことがある人
・他のNSAIDsを服用している人
・ステロイド薬を服用している人
・抗凝固・抗血小板薬(血液サラサラにする薬)を服用している人
・ビスホスホネート製剤(骨粗鬆症治療薬)を服用している人
副作用を予防するためには
以下の方法によって、胃腸障害のリスクを減らすことができます。
・多めの水と飲む、食後に飲む
薬と胃粘膜との物理的接触を避けることができます。
・予防薬と一緒に飲む、胃を守る成分が含まれている市販薬を選ぶ
予防薬なしでNSAIDsを服用していると、10~15%程度の頻度で胃潰瘍を起こすというデータがあります。
病院では予防薬が一緒に処方されたり、市販薬には胃を守る成分が含まれていたりします。
NSAIDsの消化性潰瘍予防に使われる薬
胃粘膜保護薬
ムコスタ(一般名:レバミピド)
胃酸分泌抑制薬
タケプロン(一般名:ランソプラゾール)
ネキシウム(一般名:エソメプラゾール)
ガスター(一般名:ファモチジン)
・長い間飲み続けない
数ヶ月単位で長期間服用すると、胃腸障害などの副作用が起こる頻度も上がってしまいます。
解熱鎮痛剤は根本的な治療薬ではありませんので、3~5日飲んでも症状が改善されない場合は病院への受診をおすすめします。
まとめ
解熱鎮痛剤は身近な薬ですが、胃を荒らしてしまうことがあります。
短期間や頓服での服用はリスクは少ないものの、注意しておきたい副作用です。
服用する際には、医者や薬剤師、市販薬では説明文の指示に従うようにしましょう(*^^*)
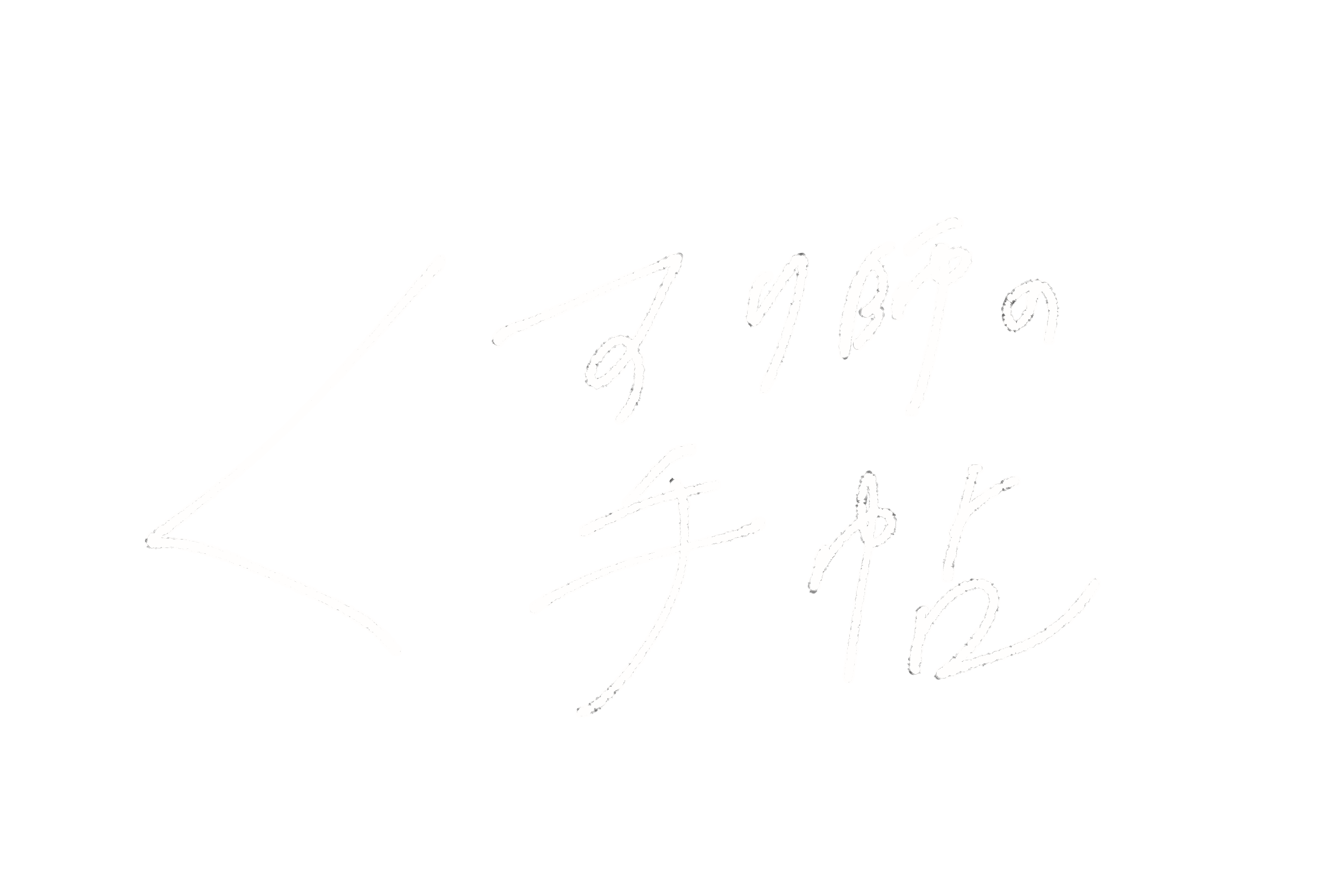
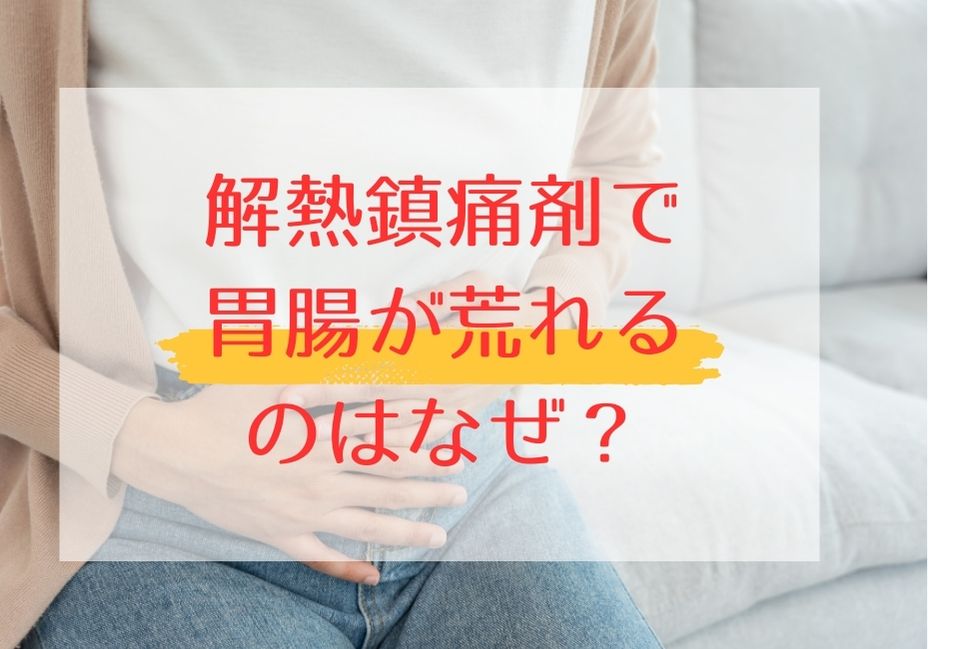
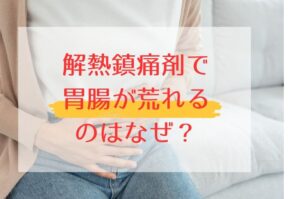









コメント