年金と聞くと、高齢者のイメージが大きいかもしれませんね。
若い世代は身近に感じにくい話題ですが、今後の生活に深く関わりますので知っておいて損はないです。
今回は、そもそも年金とはどのようなものなのか解説します。
どうやって年金ができたの?
年金は、高齢になり働けなくなっても生活できるよう、国民で支え合う制度です。
このような制度は、古代ローマ時代から既にあったとされています。
我が国では、明治時代の軍人恩給からだそうです。
最初は、公務員が公務のために死亡や公務による傷病のために退職した場合、これらの者及びその遺族の生活の支えとして給付されていました。
その後、会社員、自営業者にも支給されるようになっていきました。
1961年に、現在の国民皆年金制度が設立しました。
年金の種類は?
年金は3階建てと表されることが多いです。
1~2階は国が運営する公的年金で、3階は企業や個人が任意で加入する私的年金になります。
公的年金:国民年金、厚生年金
私的年金:企業年金、国民年金基金、個人確定拠出型年金(iDeCo)など
1階部分
国民年金は、日本在住の20歳以上60歳未満のすべての人に加入が義務付けられています。年金の土台になります。
2階部分
国民年金に上乗せする公的年金です。厚生年金は、会社員や公務員に加入が義務付けられてます。
3階部分
1~2階の公的年金に上乗せして、企業や個人が任意で加入するのが私的年金になります。

iDeCoは国民年金加入者のみで60歳以上でないと引き出せないのに対し、NISAは18歳以上であれば運用でき、いつでも引き出すことができます。
これからは、多くの人が関わる公的年金についてお伝えします。
どこからお金が出ているの?
公的年金は、「保険料」「国庫負担」「積立金」の3つの財源によって成り立っています。
このうち保険料に関しては、「賦課方式」によって行われています。年金は、自分が積み立てた貯金というイメージを持たれる方が多いですが、実際は今の若い人が払っている保険料がそのまま今の高齢者の年金に使われるという仕組みです。
ちなみに、公的年金を導入しているほとんどの国で賦課方式が選ばれています。
昔は年金の給付額(支出)にあわせて保険料(収入)を変動させていました。しかし少子高齢化の今、多い高齢層の年金を少ない若年層の保険料でまかなうのは、若年層にとって負担が大きすぎます。
このような背景から、2004年に「マクロ経済スライド」と呼ばれる制度に変わりました。
保険料(収入)にあらかじめ上限を決めておき、それに合わせて年金(支出)を出すことで、適正な保険料で若年層の負担が大きくならず、年金制度の維持がしやすくなっています。
保険料はいくら払う?
被保険者(年金を払う対象者)により3つのタイプに分けられます。
対象者:自営業者、学生、無職(20歳以上60歳未満)
払う保険料:国民年金保険料(月額※)
※毎年見直しされる(2024年度は16,980円)
支払い方:現金払い、口座振替、クレジットカードで納付、電子納付
対象者:会社員、公務員
払う保険料:厚生年金保険料(標準報酬月額※や標準賞与額※の18.3%)
支払い方:毎月の給料から天引き
標準報酬月額:会社から受け取る月額報酬(控除前の額面)を切りの良い幅で区分したときの額
標準賞与額:労働の対象として受け取る賞与のうち年3回以下のもの
対象者:第2号被保険者に扶養されている配偶者(20歳以上60歳未満)
払う保険料:国民年金保険料(配偶者の厚生年金保険料に含まれている)
支払い方法:第2号被保険者の配偶者が一緒に支払う
何がもらえるの?
公的年金では、「老齢給付」「障害給付」「遺族給付」を受けることができます。
老齢給付
65歳になった翌月から、死亡する月まで2ヶ月毎に受けられる給付
基本65歳からですが、受け取る年齢を繰上げたり繰下げたりすることができます。
・繰上げ:早くもらう分、年金額が減る
・繰下げ:遅くもらう分、年金額が増える
障害給付
病気や怪我により、一定の条件を満たす場合に受けられる給付
遺族給付
公的年金の被保険者や年金受給者が死亡したときに遺族が受けられる給付



公的年金について、自分がどれくらい受け取れるかは 厚生労働省の特設サイト「公的年金シミュレーター」で試算できます。 https://nenkin-shisan.mhlw.go.jp/
まとめ
・年金は、老後を安心して生活するために国民同士で支え合う制度
・年金には公的年金と私的年金があり、公的年金には加入義務が、私的年金は任意で加入できる
・その人のステータスにより、支払う保険料が異なる
・公的年金は、保険料と税金と積立金でまかなわれている
・年金として、老齢給付と障害給付と遺族給付がある
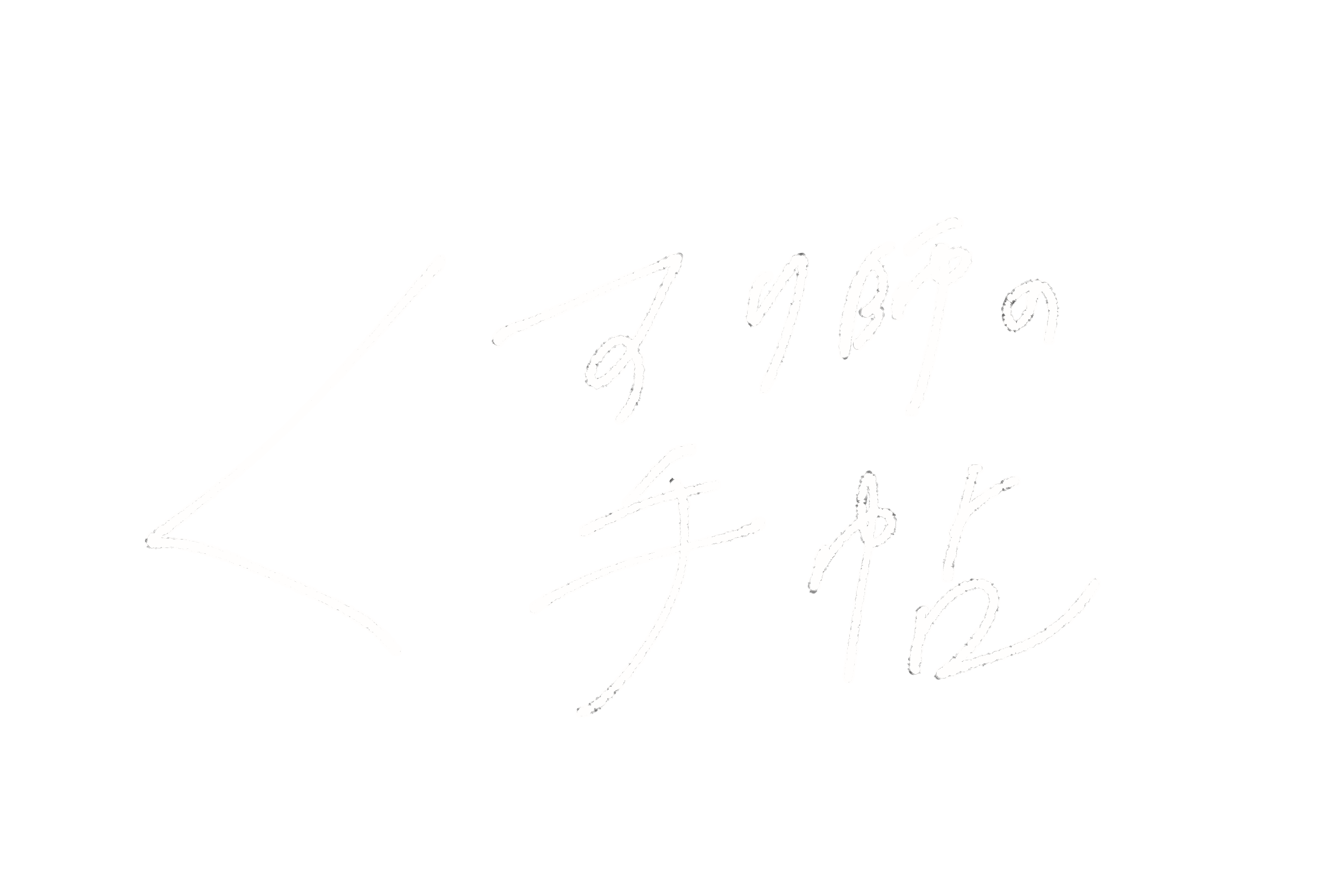
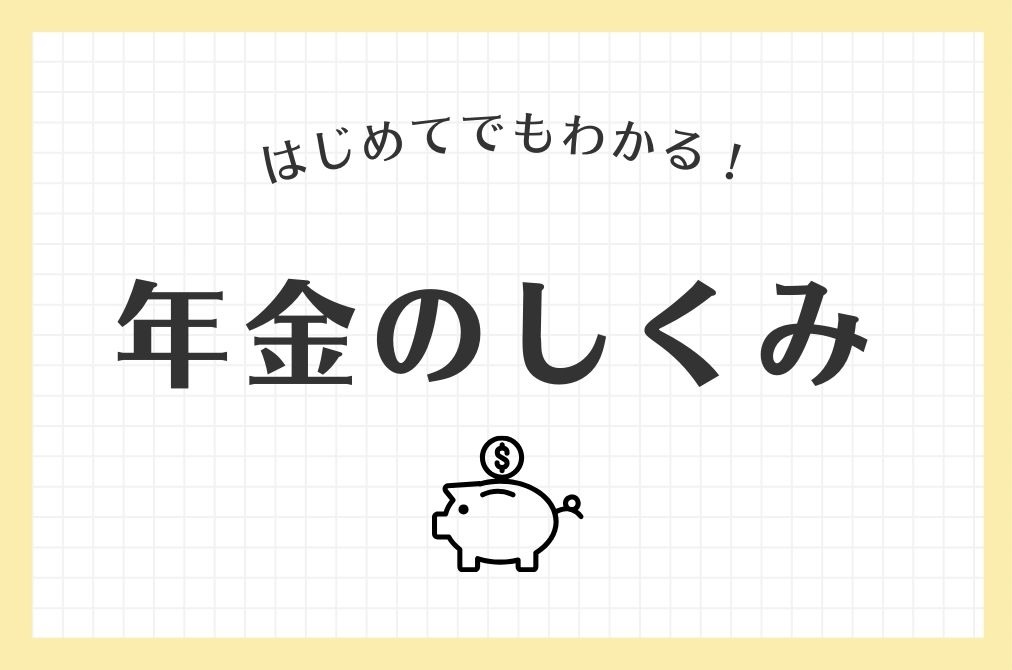
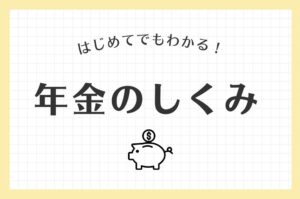

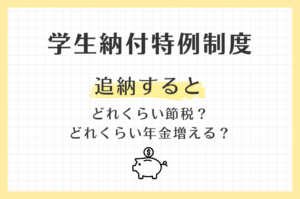
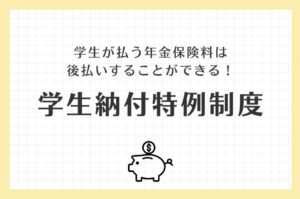
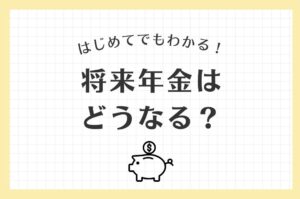
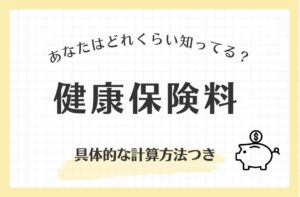
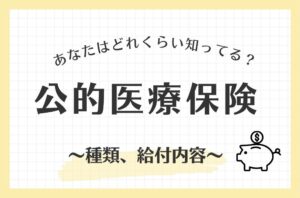
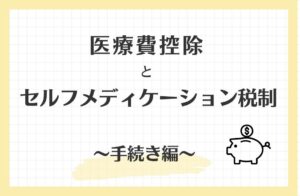
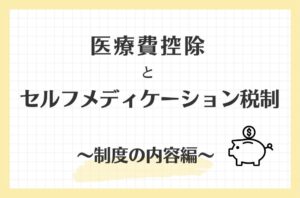
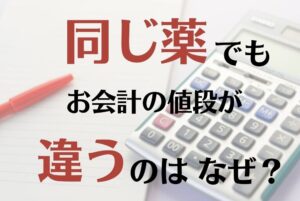
コメント