少子高齢化の社会で、若い自分たちは将来年金がもらえなくなるかも…
そんな話を聞いたことがあるかもしれません。
今回は、将来年金はどうなっていくのか、財政のしくみからまるごとお伝えします!
そもそも年金の財政のしくみは?
公的年金は、「保険料」「国庫負担」「積立金」の3つの財源によって成り立っています。
保険料の徴収方法は大きく分けて「積立方式」と「賦課方式」があります。
そのうち我が国では、「賦課方式」を採用しています。
積立方式
現役世代が支払った保険料が将来の各々の年金になる方式です。
貯金に近いイメージになります。
賦課方式
現役世代が支払った保険料が、その時代の年金受給者世代の年金になる方式です。
仕送りに近いイメージになります。
国民年金が出来た時代は積立方式を採用していました。
しかし、現役世代の時に一定の金額を積み立てておいても、年金受給世代にインフレ※が起こると積立金の価値が下がってしまう可能性があります。
※物価が上昇し、お金の価値が下がる現象
日本でも戦後の急激なインフレが起こり、年金の運用が難しくなりました。
一方で賦課方式は、現役世代の保険料がそのままその時代の年金になるので、お金の価値が変わりません。
予測できない社会や経済の変化の中で、年金の実質的なお金の価値を維持するために、賦課方式を基本とする運営に変わってきました。
少子高齢化で年金制度が破綻する?!
賦課方式は実質的なお金の価値を維持できるメリットがある上で、保険料を払う世代と年金を受給する世代のバランスが変わると運営が難しくなるというデメリットもあります。
今までは、年金の給付水準を維持するために保険料を変動させる「財政再計算」を行っていました。
日本の急激な少子高齢化はますます進み、年金を受給する世代が増え、保険料を払う世代が減っています。このまま年金を同じ水準で支給しようとすると、保険料が高くなり現役世代の負担が大きくなってしまいます。

年金制度が破綻し、年金がもらえなくなってしまうのではないかと言われるのはこの背景があるからです。
年金を守るため改革が行なわれた!
上記の内容などを考慮して、公的年金を維持していくため、2004年に根本的な改革が行われました。
(1)上限を固定した上での保険料の引き上げ
2017(平成29)年度以降の保険料は、上限が決められました。
厚生年金:標準報酬月額の×保険料率(18.3%)(労使折半なので労働者の支払い分は9.15%)
国民年金: 17,000円×保険料改定率 (2024年度は16,980円)



2024年度現在では厚生年金の保険料率は上限に達しているため、現在の制度ではこれ以上保険料が上がることはありません!
国民年金の保険料は物価や賃金の上がり下がりをみて調整されています。
(2)基礎年金国庫負担割合の2分の1への引上げ
2009(平成21)年度以降は、基礎年金給付費に対する国庫負担割合を3分の1から2分の1に増やすことで、年金の財源を確保できるようにしています。
(3)積立金の活用
将来の年金給付に充てるため、おおむね100年間の規模で積立金を運用しています。
(4)財源の範囲内で給付水準を自動調整する仕組み(マクロ経済スライド)の導入
賃金や物価が上昇した時のみ、年金の増額を抑えて、その分を将来の為にまわしています。
このように、国ではその時の状況に合わせて対策を行っています。ですので、公的年金制度がなくなったり年金がゼロになることはありません。
加えて、「財政再計算」は、公的年金の財政の検証を定期的に行う「財政検証」へ移行しました。
財政検証では何してる?
公的年金の財政バランスは、社会情勢や人口構成比によって日々変わっています。
そのため少なくとも5年に一度経済や人口の現状を織り込んで、今後100年間の見通しを立てる「財政検証」を行っています。
財政検証においては、主に以下の2点について検証しています。
・長期的な給付と負担の均衡が確保されるか
・均衡が確保される給付水準はどの程度になるか
現在、国ではモデル年金の所得代替率※が将来的に50%を下回らないようにすることを目標としています。
「所得代替率」
年金を受け取り始める時点の金額が、現役男性会社員の「ボーナスを加味した手取り収入額」に対してどのくらいの割合かを示す数値。
2024年度の財政検証による所得代替率
今後も同じ経済状況と考える「過去30年投影ケース」でも、100年後まで所得代替率は50%をきっていないことがわかります。
ただし、ここでのモデル年金は「平均的な給料額で40年間働いた夫」と「40年間専業主婦であった妻」の2人が受け取る年金の合計です。
近年では多様な働き方があり、このモデルが時代に合っているのかは怪しいところです…
まとめ
・現在の年金は「賦課方式」で運営している
・公的年金を維持してくため、2004年に年金制度が改定された
・「財政検証」を通して年金の状態は定期的にチェックされている
年金の給付が全くなくなる可能性はありませんが、年々減少していくのは避けられません。
年金は補助として、個人で老後資金をつくっていくのが良いでしょう。
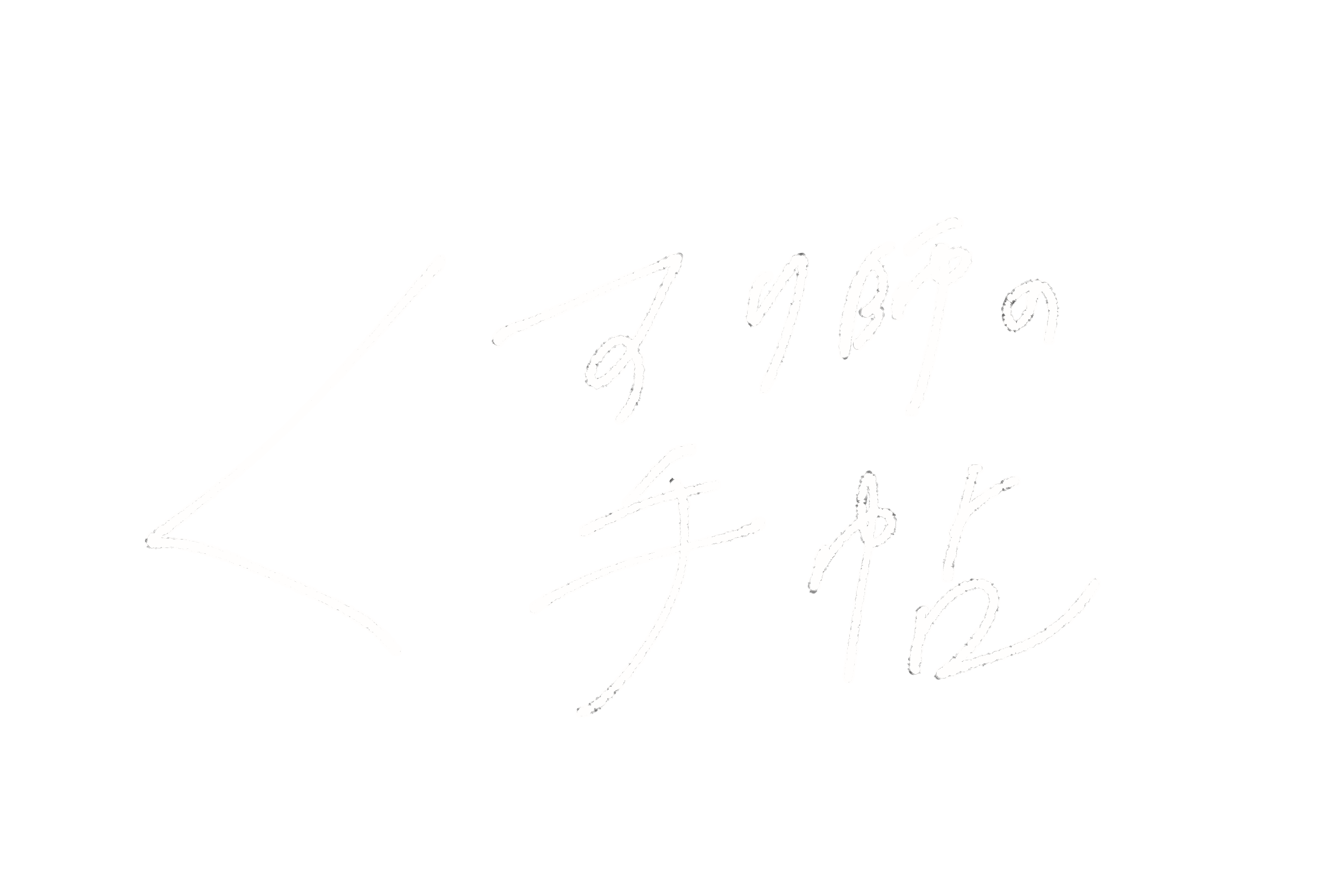
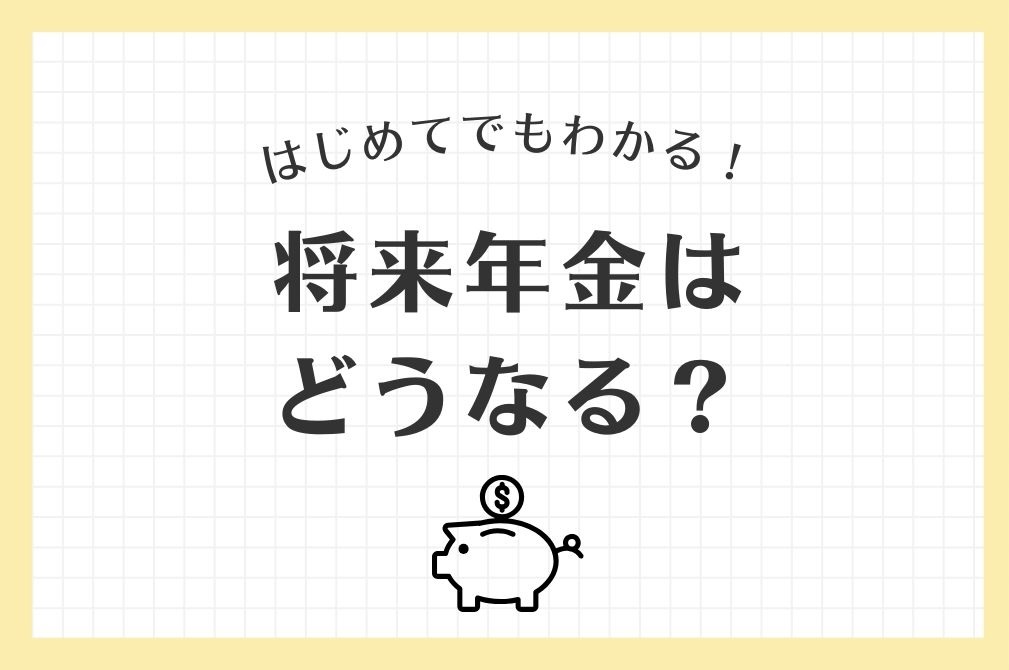
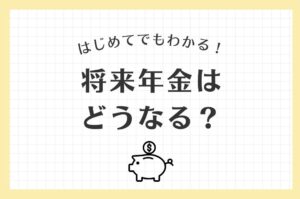

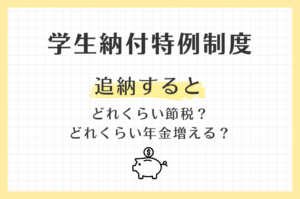
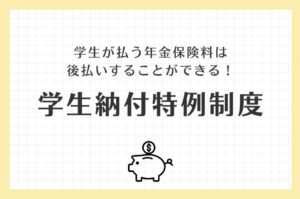
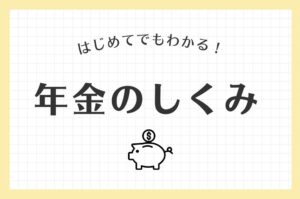
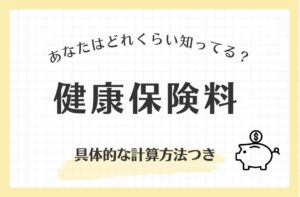
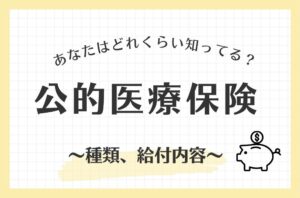
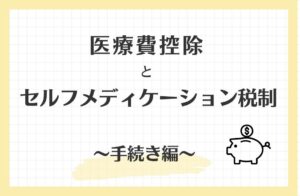
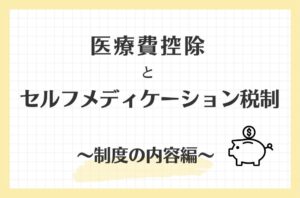
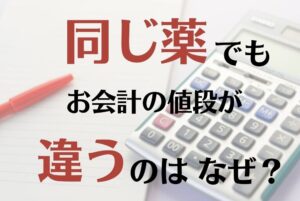
コメント