令和6年10月から、後発医薬品(=ジェネリック医薬品)がある先発医薬品の選定療養制度が始まりました。
対象の先発医薬品を患者様の希望で選ばれる場合、特別料金をいただくようになります。
そもそも選定療養制度とは何なのか、特別料金の計算方法まで解説します!
選定療養制度とは
日本の公的保険医療制度では、公的保険が適用される診療と公的保険が適用されない診療の併用は認められていません。
保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十五号)
(特殊療法等の禁止)
第十八条
保険医は、特殊な療法又は新しい療法等については、厚生労働大臣の定めるもののほか行つてはならない。
同じ疾患に対して両者が混在する場合、一連の治療とみなされ、公的保険は適用されず全て保険外診療となります。
しかし、医薬品の適応外使用や将来の医療技術の発展、療養環境等による患者さまのニーズなどに適切に対応すべく、厚生労働大臣が定める療養は保険外併用を認める「特定療養費」が1984年に導入されました。2006年10月からは「保険外併用療養費」に置き換わりました。
保険外併用療養費には、「評価療養」「選定療養」「患者申出療養」の3種類あります。
| 評価療養 | ①先進医療(高度医療)を含む ②治験にかかる診療 ③医薬品医療機器当法の承認後で保険収載前の医薬品、医療機器、再生医療等製品の使用 ④薬価収載医薬品の適応外使用 など |
| 選定療養 | ①特別の療養環境(差額ベット) ②歯科の金合金等 ③金属床総義歯 ④予約診療 ⑤時間外診療 ⑥大病院の初診 ⑦小児虫歯の指導管理 ⑧180日以上の入院 ⑨後発医薬品がある先発医薬品の使用 など |
| 患者申出療養 | 高度の医療技術を用いた療養であって、患者の申出に基づき臨床研究中核病院等から申請され国が承認した医療行為 |
その選定療養で、令和6年10月から「後発医薬品がある先発医薬品(長期収載品)の選定療養」が新たに加わりました。
なぜ長期収載品の選定療養が導入されたのか
この制度の背景には、国民医療費の増加阻止があります。
国民医療費は年々増加しており、このまま進むと支出が多くなりすぎて公的医療保険制度は破綻してしまうと言われています。
医療費を適正化するため、2008年から国で見直しが行われてきました。その中の対策の一つとして「後発医薬品の使用促進」が行われています。先発医薬品よりも価格が低い後発医薬品の割合を増やすことで、医療費を削減することができるからです。

選定療養により先発医薬品に特別料金を上乗せすることで、より多くの患者様に後発医薬品への切り替えを検討してもらおうとしています。
選定療養の対象となる「長期収載品」とは
長期収載品については、次の(1)から(3)までを全て満たすものとされています。
(1) 後発医薬品のある先発医薬品(いわゆる「準先発品」を含む。)であること(バイオ医薬品を除く)。
(2) 後発医薬品が収載された年数及び後発品置換え率の観点から、 組成及び剤形区分が同一であって、次のいずれかに該当する品目であること。
① 後発医薬品が初めて薬価基準に収載されてから5年を経過した品目(後発品置換え率が1%未満のものは除く。 )② 後発医薬品が初めて薬価基準に収載されてから5年を経過しない品目のうち、後発品置換え率が 50%以上のもの
(3) 長期収載品の薬価が、後発医薬品のうち最も薬価が高いものの薬価を超えていること。この薬価の比較にあたっては、組成、規格及び剤形ごとに判断するものであること。

簡単にまとめると、選定療養の対象になる長期収載品は、後発医薬品が5年以上販売されていたり、多くシェアされている先発医薬品になります!
長期収載品については、以下のサイトで見ることができます。
後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について|厚生労働省
ただし、例外があります。
・医療上必要があると認められる場合
・病院若しくは診療所又は薬局において後発医薬品を提供することが困難な場合
・先発医薬品の薬価が後発医薬品の薬価以下の場合
医療上必要があると認められる場合とは
医師又は歯科医師において、次のようなケースでは、長期収載品の処方等又は調剤をする医療上の必要があると判断されます。
① 長期収載品と後発医薬品で薬事上承認された効能・効果に差異がある場合であって、その患者の疾病の治療のために必要な場合
② その患者が後発医薬品を使用した際に、副作用があったり、先発医薬品との間で治療効果に差異があったと判断する場合であって、安全性の観点等から必要な場合
③ 学会が作成しているガイドラインにおいて、長期収載品を使用している患者について後発医薬品へ切り替えないことが推奨されている場合
④ 後発医薬品の剤形では飲みにくい、吸湿性により一包化できないなどの場合(単に剤形の好みという理由では認められません。この場合の判断は薬剤師が行うこともできます)



医療上必要だったり、後発医薬品が流通の関係等で準備出来ない場合は先発医薬品でも特別料金はかかりません。
どれくらい特別料金がかかる?
特別料金は、先発医薬品とその後発医薬品の価格差のおおよそ4分の1の料金になります。
(例)
アムロジンOD5mg 1回1錠 1日1回 朝食後 30日分 3割負担の場合
| 長期収載品 | 薬価 | 後発品最高価格 | 差額の1/4 |
| アムロジンOD錠5mg | 15.2円 | 10.1円 | 1.28円 |
【1日分あたりの差額】1.28円×1錠=1.28円
薬価の計算は 15円以下は10円、15.1円以上は五捨五超入というルールがあるので、1.28円は10円になる。
【処方日数あたりの差額】10円×30日=300円
特別料金は消費税がかかるので、300円×1.1(消費税)=330円
特別料金は保険医療機関の利益になる?
保険医療機関は、全体の医療費のうち患者負担以外の残りの医療費(保険給付)を、保険者に請求して支払って頂いています。
選定療養の特別料金は保険医療機関が徴収しますが、後から頂く保険給付から特別料金分が差し引かれています。
ですので実質は患者負担分と保険給付分しか頂いておらず、保険医療機関の利益になることはありません。
まとめ
・医療費の適正化のため、後発医薬品の使用率を上げるべく「後発医薬品がある先発医薬品での選定療養」が始まった
・後発医薬品が多く広まっている先発医薬品が対象だが、医療上必要な場合や後発医薬品の在庫がない場合は特別料金はかからない
・特別料金は先発医薬品と後発医薬品の値段の差から計算される
・特別料金は公的医療機関の利益とはならない
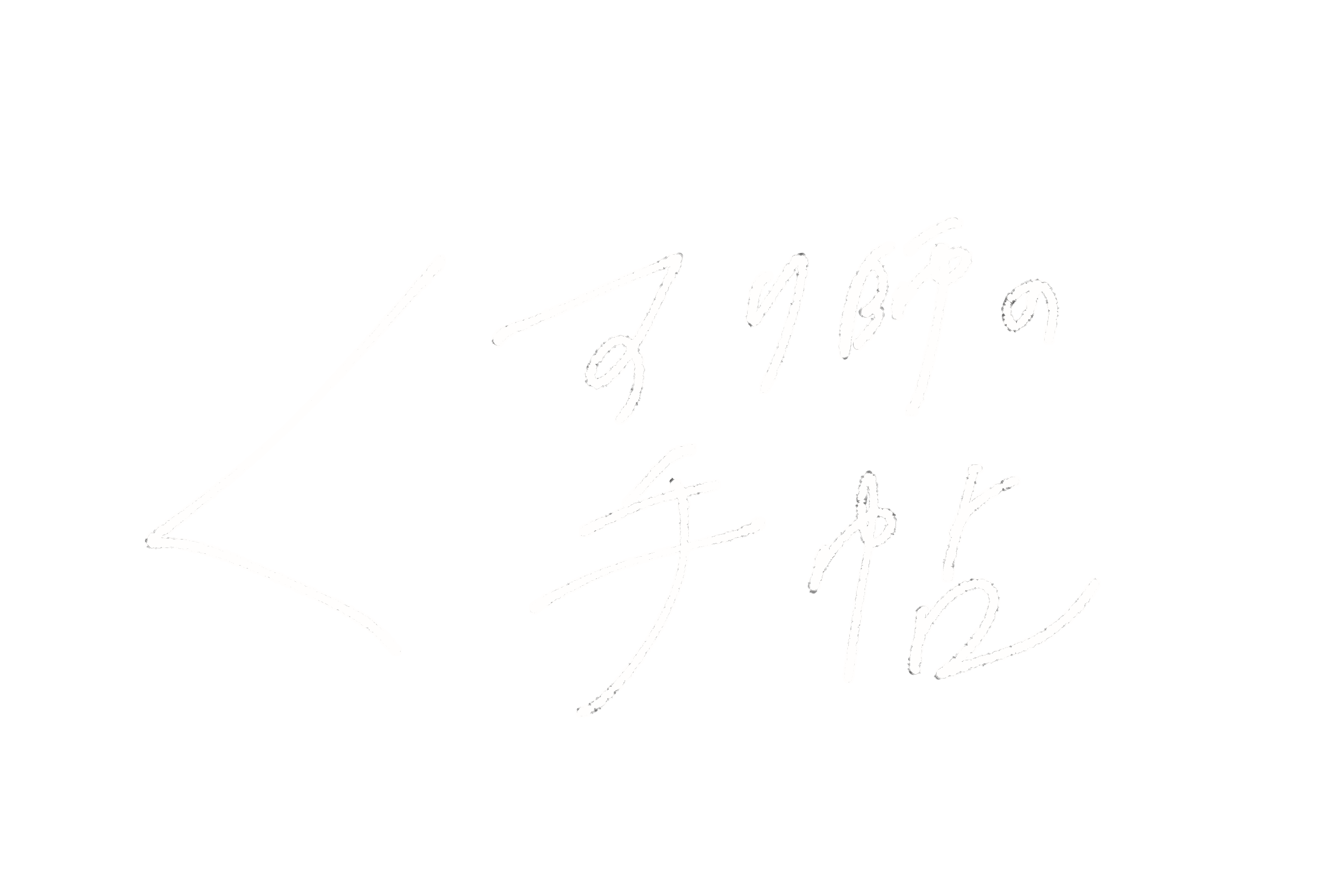











コメント