日本国内に住む全ての人は、20歳以降から国民年金の保険料を支払わなくてはなりません。
しかし、学生の場合は「学生納付特例制度」を利用することができます。
どのような制度なのか分かりやすく解説します!
そもそも学生が払う年金保険料はいくら?
年金は、高齢になって働けなくなっても生活できるよう、国民で支え合う制度です。
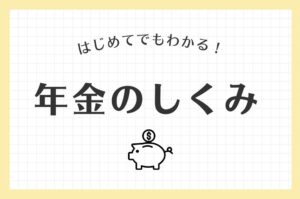
年金といったら老後にもらえるお金のイメージが大きいですが、病気や怪我の時にもらえるお金や遺族のためのお金もあります。
| 歳をとった時 | 障害になった時 | 遺族になった時 | |
| 国民年金 | 老齢基礎年金 付加年金 | 障害基礎年金 | 遺族基礎年金 寡婦年金 死亡一時金 |
| 厚生年金 | 老齢厚生年金 | 障害厚生年金 障害手当金 | 遺族厚生年金 |
これら年金の財源の一つとして、現世代の保険料があり、我が国では20歳になった時点から保険料を払う義務が課せられます。
その人のステータス(学生、会社員、専業主婦(夫)など)によって支払う保険料の種類が異なっており、学生の場合は国民年金の保険料を支払います。
国民年金の保険料は、2024年度だと毎月16,980円です。

学生が毎月2万円弱払うのはしんどいですね…
このような経済負担を軽減できる制度が、「学生納付特例制度」です。
「学生納付特例制度」とは
学生納付特例制度は、所得が一定水準以下※の20歳以上の学生が、経済的な負担を軽減しながら国民年金の加入義務を果たせる制度です。
※所得基準(申請者本人のみ)128万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等
この制度を利用すると、学生である間は国民年金保険料の支払いが猶予されます。保険料を払えない場合でも年金加入資格を維持できるため、将来の年金受給に備えることができます。
「学生納付特例制度」のメリット
1.経済的な負担を軽減
この制度を使えば、在学中は国民年金の保険料の支払いを後回しにできます。
2.未納扱いにならない
制度を利用することで、「未納」ではなく「猶予」として扱われ、将来の年金受給資格に影響を与えません。
3.追納で節税ができる
社会人になって保険料の後払い(追納)を行った場合、所得税と住民税を少なくすることができます。
「学生納付特例制度」のデメリット
1.追納には期限と加算額がある
猶予された保険料は後から追納できますが、以下の点に注意が必要です
追納の期限
猶予された年度の翌年度から10年以内です。それを過ぎると支払えなくなり、完全な未納扱いとなります。
加算額
追納する際には、3年以上経過した保険料に加算額(約15~20%)が付けられます。そのため、長期間放置すると、追納額が大幅に増える可能性があります。
2.追納しない場合、将来の年金額が減る
追納せず「未納」になる場合は、その分、老齢基礎年金の金額が減少します。
3.毎年手続きを行う必要がある
学生納付特例制度を利用するには、毎年申請手続きを行わなければなりません。これを怠ると未納扱いとなり、制度のメリットが受けられません。
「学生特例納付制度」の申請方法
電子申請
マイナポータルから、いつでもどこでもペーパーレスで申請することができます。
窓口・郵送
年金事務所や市区役所・町村役場の国民年金担当窓口で、申請または郵送申請ができます。
最寄りの年金事務所は「全国の相談・手続き窓口」のページをご覧ください。
まとめ
学生納付特例制度は、経済的負担を軽減しながら将来の年金制度への影響を最小限に抑えられる便利な制度です。
ただし、追納が重要であることを理解し、将来のライフプランに合わせて計画的に支払っていきましょう!


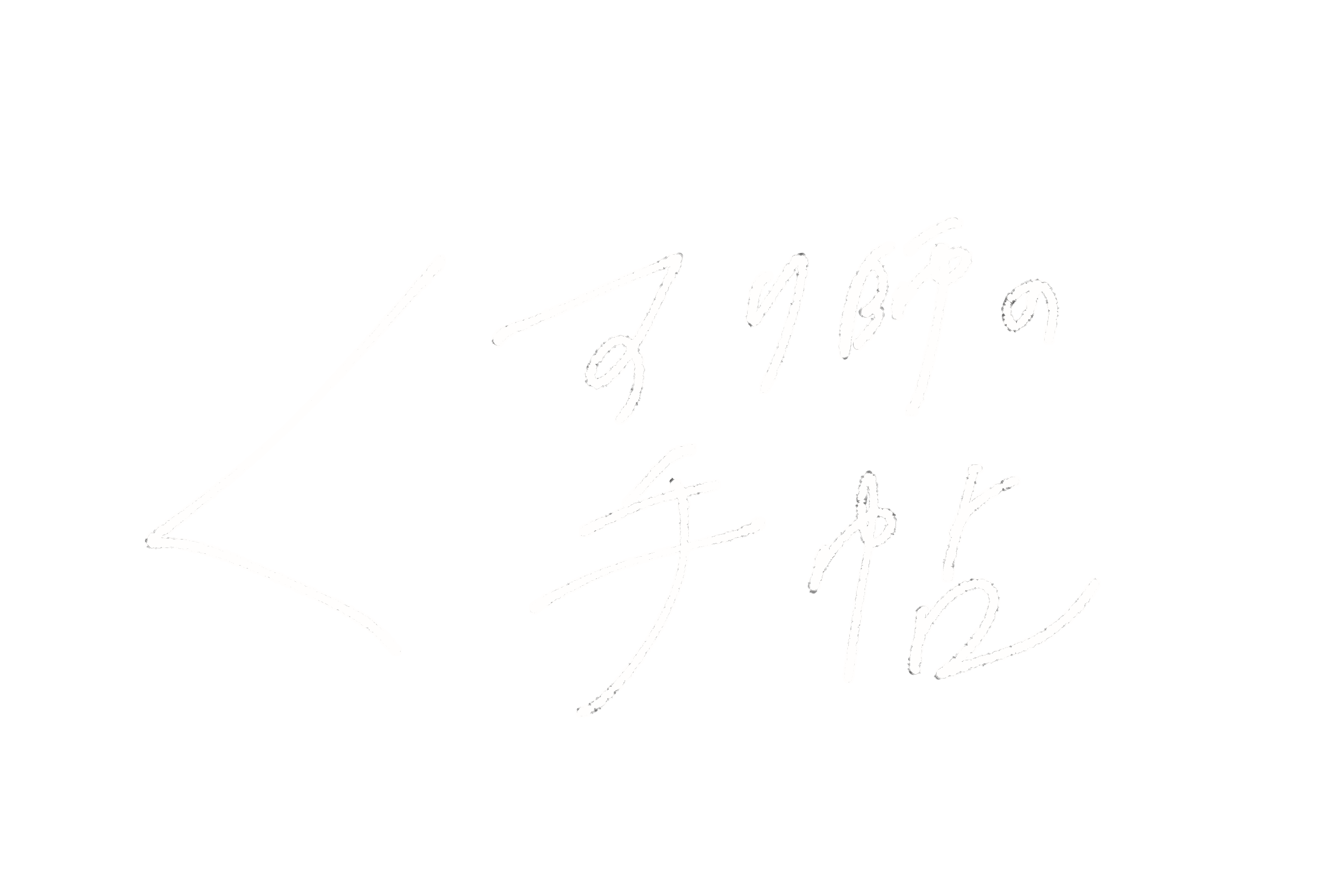
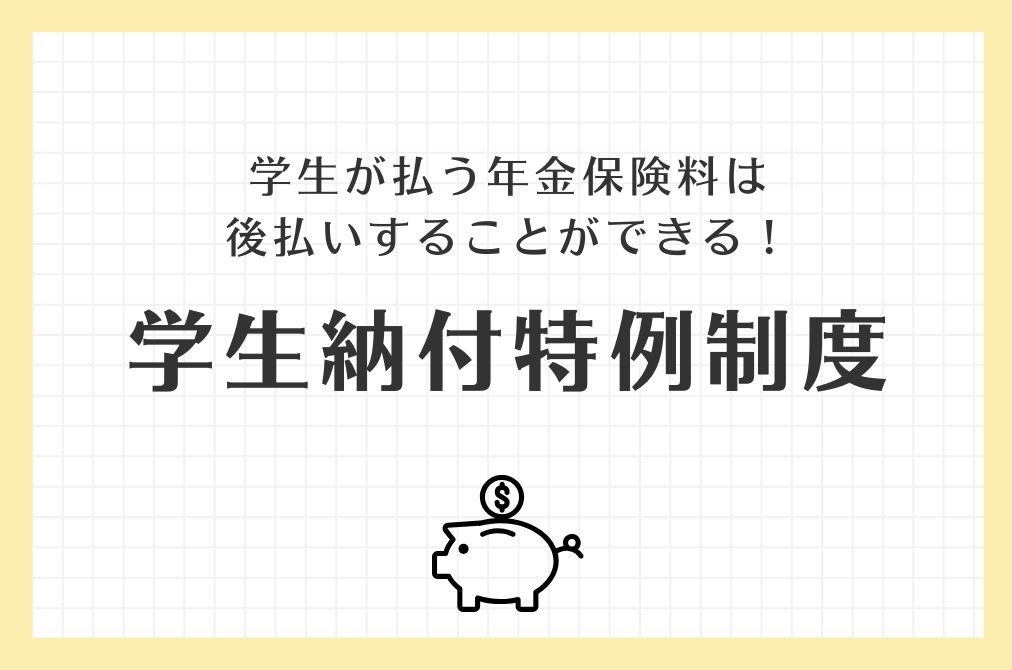
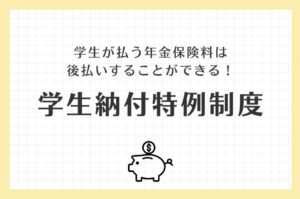

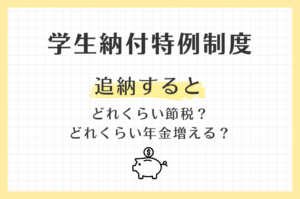
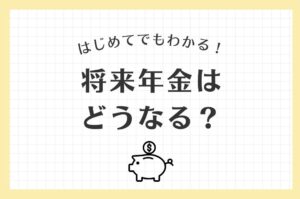
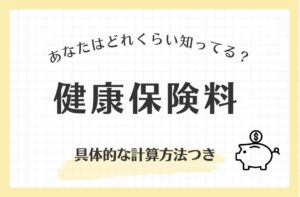
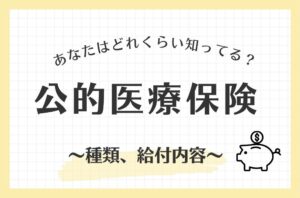
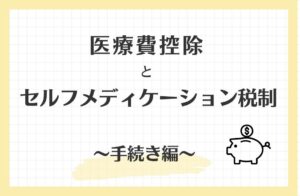
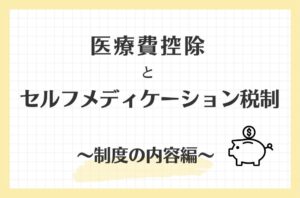
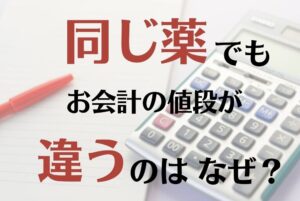
コメント