お薬は、一緒に飲む飲料によって効果に差が出てしまうことがあります。
今回はその中でも「牛乳」の飲み合わせについてみていきましょう!
牛乳で飲み合わせが悪くなる原因
牛乳がお薬に影響する原因は主に3つあります。
①カルシウム
牛乳は栄養価が高い飲料で、特にカルシウムが多く含まれています。カルシウムは人体に必要な栄養素の一つで、骨や歯はもちろん血液、筋肉、神経などの組織にも使われています。
お薬の一部では、カルシウムと合体(キレート形成)し吸収が落ちてしまいます。
②脂肪分
牛乳は87.4%の水分と12.6%の乳固形分(3.8%の乳脂肪、8.8%の無脂乳固形分)でできています。乳脂肪には、体内で合成されない必須脂肪酸、脂溶性ビタミン(A、D、E)などが含まれています。
お薬の中には脂に溶けやすいものがあり、牛乳と一緒に飲むと吸収が上がってしまう場合があります。
③胃酸を中和する
牛乳のあらゆる成分が胃酸に関係しますが、そのうちタンパク質(主にカゼイン)は、胃酸と反応して一部が固まる性質があります。この過程で胃酸を一時的に消費するため、胃酸が薄まります。
体内で溶ける場所を設計してつくられている薬は、胃酸が中和されることで狙った効果が得られないことがあります。
カルシウムと相性が悪い薬
抗菌薬
抗菌薬の一部では、カルシウムと合体(キレート形成)してしまい、体内への吸収が出来なくなってしまいます。
テトラサイクリン系抗菌薬
ニューキノロン系抗菌薬
セフジニル
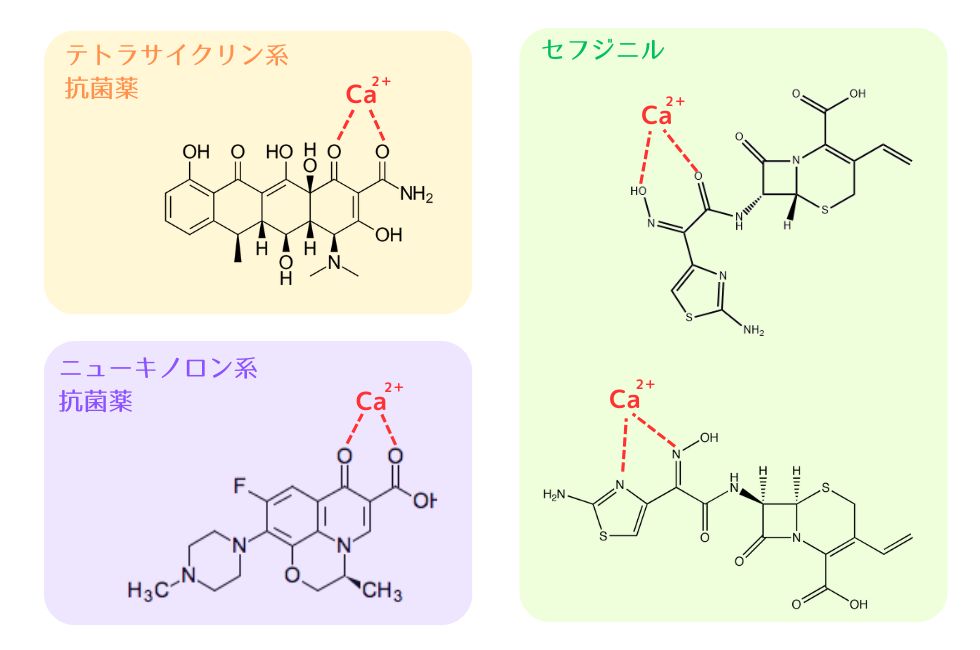

お薬との間隔2時間を空けてもらえれば、牛乳を飲むことができます
骨粗鬆症治療薬
骨粗鬆症治療薬のうちビスホスホネート製剤では、抗菌薬と同様、カルシウムと合体すると体内に吸収されにくくなってしまいます。
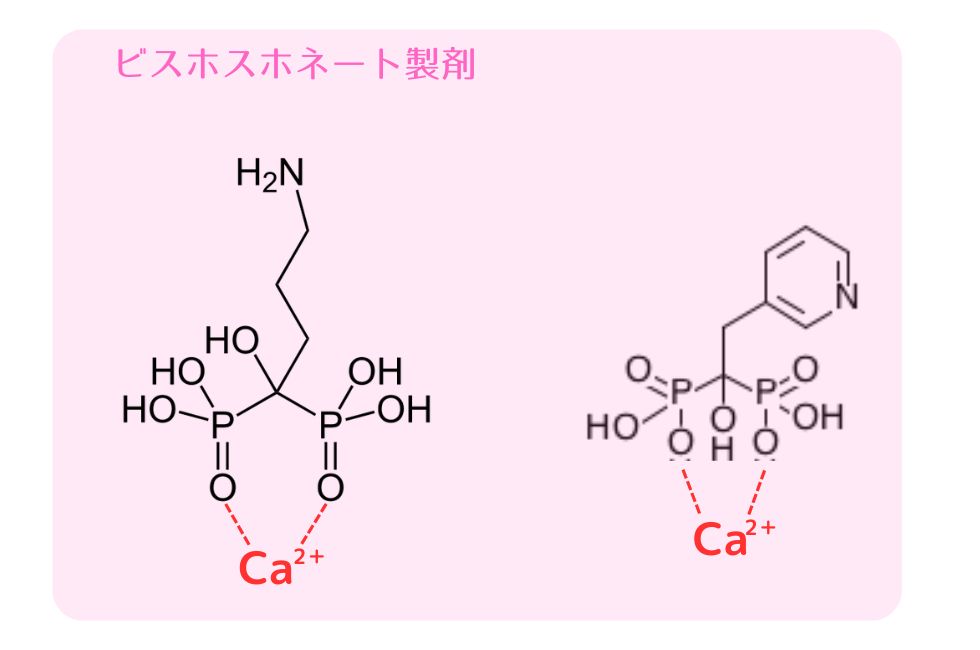
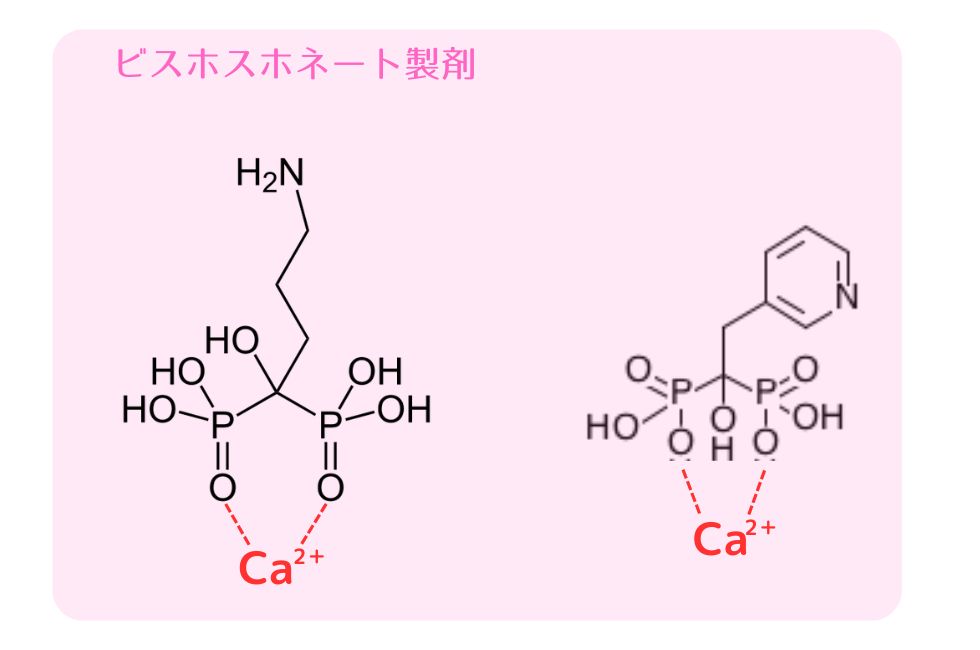



しかも、ビスホスホネート製剤はお薬自体が吸収されにくいです。さらなる吸収低下を防ぐため、服用後2時間は牛乳だけでなく食事自体をしてはいけません。
脂肪分と相性が悪い薬
クアゼパム(睡眠薬)
プロブコール(脂質異常症治療薬)
脂に溶けやすい薬だと、食べ物の脂によってさらに溶けやすくなり、体内への吸収しやすくなってしまいます。





上記の2つは吸収が上がって副作用が出るリスクがあるので、牛乳と同時に摂るのは避けましょう。
胃酸が中和されると良くない薬
腸溶性製剤
・サラゾスルファピリジン
・バイアスピリン など
薬が腸に届く前に胃で溶けてしまうため、胃を荒らしたり、薬の効果が十分に発揮されなかったりする場合があります。





最低でも服用の1時間前後は牛乳を飲むのを避けましょう。
+α:ミルク・アルカリ症候群
酸化マグネシウムなどの制酸薬や炭酸カルシウムを摂取すると、血液がアルカリに傾きます(アルカローシス)。
アルカローシスは腎臓でのカルシウムの吸収を増やします。
そのため、大量の牛乳を一緒に摂っていた場合、カルシウムが過剰に吸収され高カルシウム血症(初期症状:食欲不振、吐き気、倦怠感、頭痛など)を引き起こします。



牛乳の摂取量は、一般的に1回に500mL以下、1日に1L以下であれば問題ありません。
まとめ
・牛乳で飲み合わせが悪くなる原因は、カルシウム、脂肪分、胃酸を中和させる作用がある
・抗菌薬や骨粗鬆症治療薬の一部は、カルシウムと合体し効果が落ちる
・油に溶けやすい薬は効果が高くなり、副作用のリスクがある
・腸で溶けるように設計されている薬もあり、狙った効果が得られなくなってしまう
簡単に解説しましたが、ご自身で判断されるのはなかなか難しいです。
悩んだ場合は医師や薬剤師にご相談ください(*^^*)
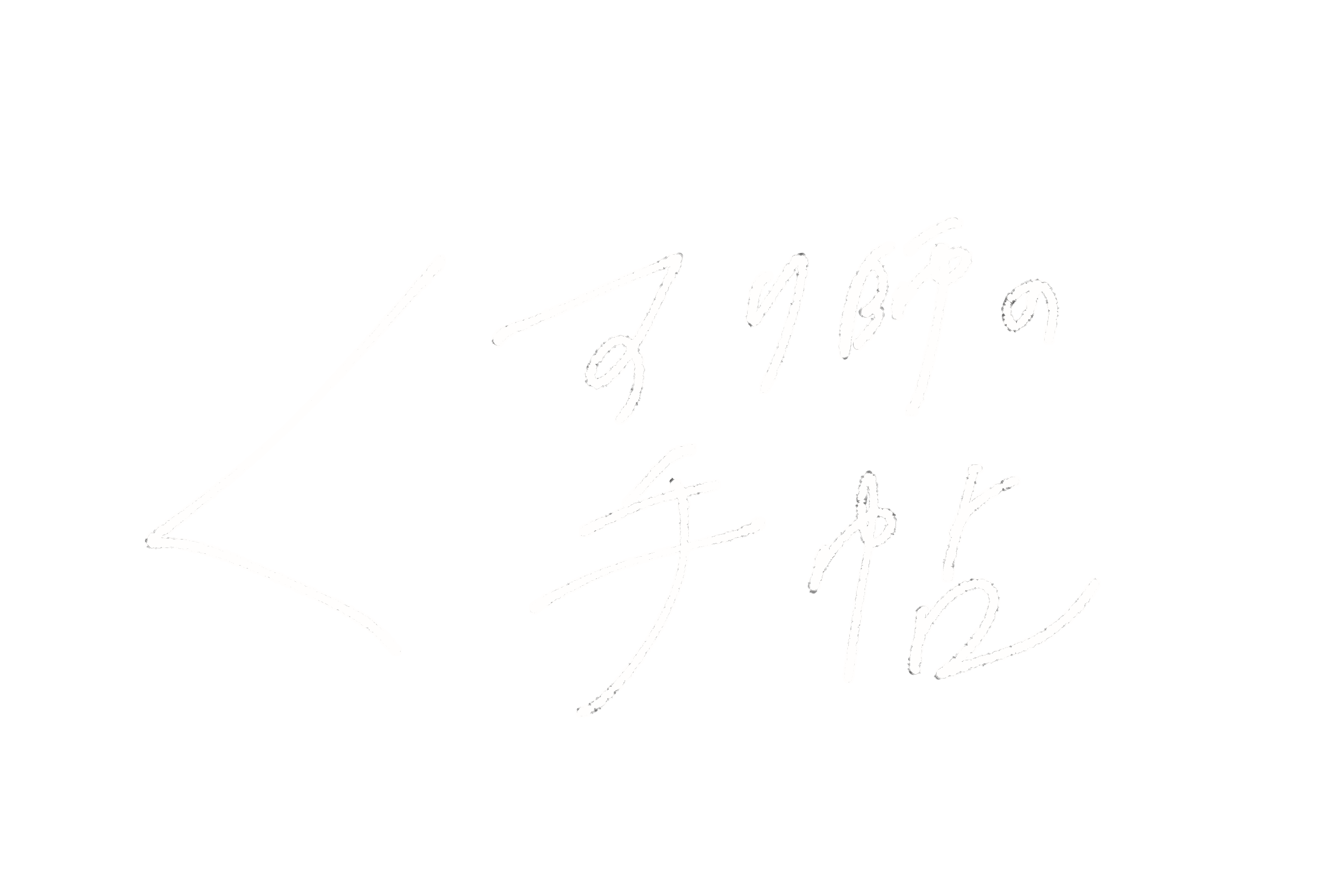











コメント