ひとえに錠剤と言っても、実は色々な種類があることをご存知ですか?
今回は、その中で一番よく聞く「口腔内崩壊錠」について解説します。
口腔内崩壊錠とは
口腔内崩壊錠は、その名の通り、口腔内で速やかに溶解または崩壊させて服用する錠剤です。
従来の錠剤やカプセル剤はコップ1杯程度の水やぬるま湯で服用する必要がありましたが、口腔内錠は口の中の唾液で数十秒で崩壊するため、唾液や少量の水分があれば服用できます。
商品名に、ODという名前がついているものが多いです。また、口腔内崩壊錠のような直ぐに崩壊しやすい錠剤でD、PRD、RMなどの名前がついたものもあります。
OD:Orally Disintegrating 口腔内崩壊
RPD:Rapid Disintegrating 速
D: Disintegrating 崩壊
RM:Rapid Melt 速溶
このうちOD錠とRM錠は、水なし水ありの区別なく生物学的同等性が確認されているため、水なしで服用可能です。
これらとは別の速崩型の錠剤は、必ず水で服用する必要があります。
詳しくは薬剤師にご相談ください。
現在の口腔内崩壊錠ができるまで
OD錠の研究開発は1980年代頃まで遡ります。
開発当初は混ぜて練った物を鋳型に流し込んで乾燥させる製法でした。錠剤内の水分が乾燥して内部に多数の細孔(小さい穴)ができ、そこに唾液が染み込んで崩壊するという仕組みです。
しかしこれでは強度が低く、シートから出す際に欠けてしまう問題などがありました。また、特別な設備が必要で製造コストもかかっていました。
製造コストを抑えるため、普通の錠剤と同じ設備にする必要性はありましたが、同一の製造方法だと高い圧力がかかってしまい、薬が硬くなりすぎてしまうという懸念点がありました。これだと口腔内崩壊錠としては適しません。
低い圧力で高い強度、かつ、よい崩壊性が得られるよう、製造技術や添加剤*の研究が進みました。
*添加剤とは?
錠剤や顆粒剤、カプセル剤などの固形剤は、有効成分と添加剤で構成されています。
各々の製薬企業が独自の製剤技術・添加剤を研究・開発し、1990年代からは普通の錠剤と同じ設備で製造できるようになりました。近年では、錠剤の製造法の中で工程の短縮が期待できる直打法での製造が行われるようになっています。
また、高い硬度や崩壊しやすさは勿論、味にもこだわり、薬本来の苦味をマスキングしているものも増えてきています。
口腔内崩壊錠が飲みやすくなっており、市場に多く出回れるのは、製薬企業の努力あってこそなんですね。
口腔内崩壊錠のメリット・デメリット
小さい頃、薬が飲みにくかったことありませんでしたか?
高齢者の方も小児の方と同じく、飲み込みの力が弱くて薬の服用が難しいことがあります。口腔内崩壊錠は唾液ですぐ溶けるため、大きい錠剤のまま飲み込まなくてよくなります。
また、頭痛や胃痛等の急な痛みにすぐ飲みたい、水分摂取制限のある患者さんにも、水なしで服用できるため適していると言えます。
加えて、簡易懸濁法(薬剤をそのまま 55℃程度のお湯に入れて溶かし、チューブから注入する方法)が簡単に行え、服薬のしやすさが広がります。製剤技術の向上により、飲みやすい味付けの薬も増えています。
①以下の方に適している
・飲み込みが難しい高齢者や小児の方
・手元に水がなくても飲みたい、飲む場所を選びたくない方
・水分摂取を制限されている方
②簡易懸濁法が簡単に行える
③飲みやすい味付けの薬が増えている
しかし、水に溶けやすい性状の裏を返せば、吸湿しやすく普通の錠剤と比べると壊れやすいという面があります。一包化が難しかったり、シートから薬を出す時に壊れやすいことがあります。
また、錠剤が口の中で崩れるため、原材料の味や食感を直接感じる場合があります。近年は飲みやすい味付けの薬も増えていますが、食感や味を不快に感じる場合も少なくありません。なお、複数の錠剤を同時に飲む場合は、味が混ざって飲みにくくなる場合もあります。
①一包化が難しい、壊れやすい
②味を不快に思う場合もある
②複数の錠剤と同時に飲まなければならない時には、味が混ざって飲みにくい。
口腔内崩壊錠でよくある質問
口の中から薬が吸収されるのか?
口腔粘膜では吸収されず、消化管で吸収されます。ですので、口の中で溶けたから効果発現が早まることはありません。
水なしで飲んだら効果が落ちる?
水なしで飲んでも、従来どおり水で飲んでも効果には差がないことが確認されています。
横になって飲んでもいい?
溶けやすい口腔内崩壊錠でも、喉周辺にお薬が残ってしまうことがあります。寝たままの状態で服用する場合は、水と一緒に流し込んでください。
まとめ
口腔内崩壊錠は、飲み込みしやすい、サッと飲めるなどメリットがある一方、味が気になるなどデメリットもあります。
ご自身の生活スタイルや状態に合わせて、医師や薬剤師と相談しながら薬の種類を決めていきましょう!
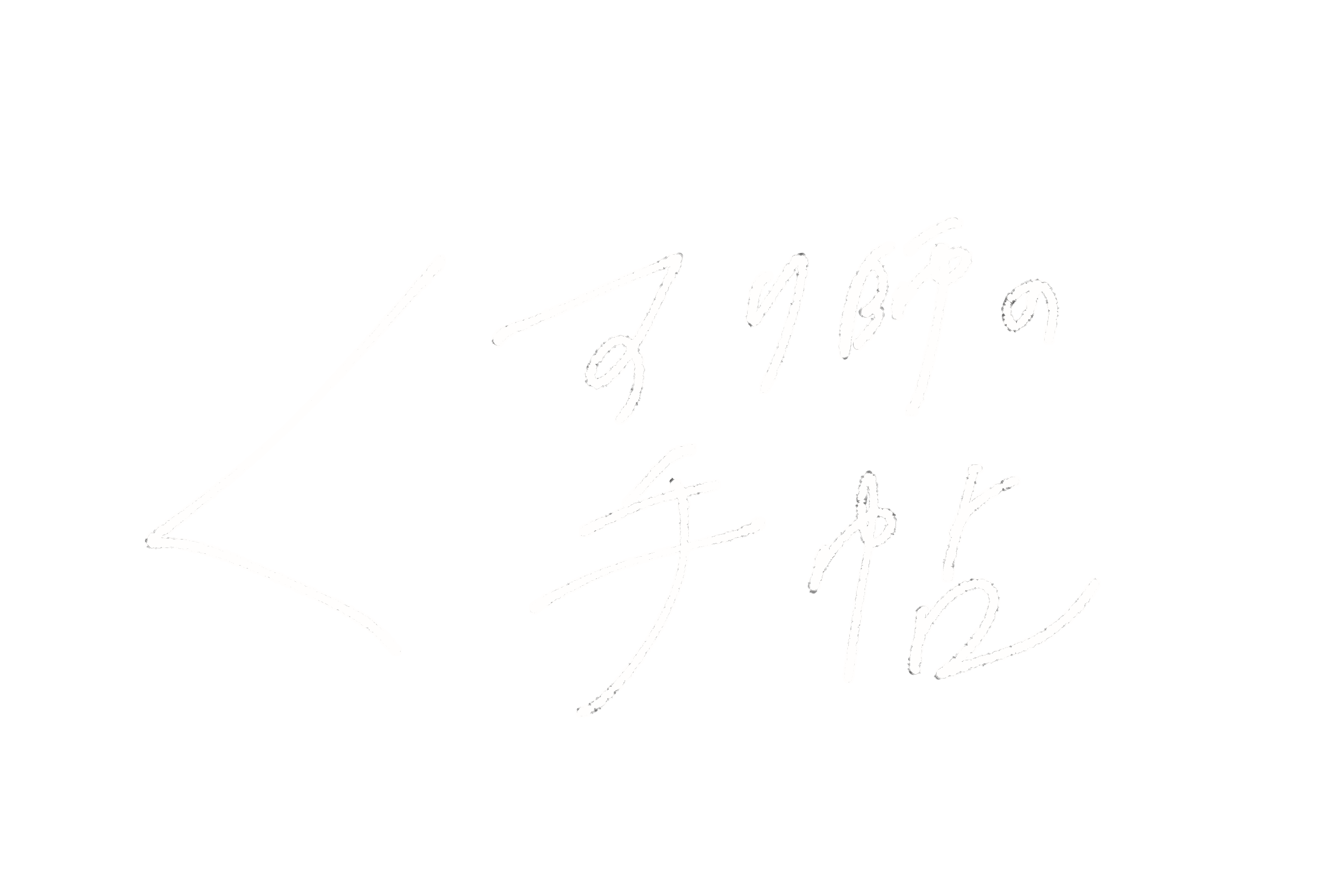











コメント